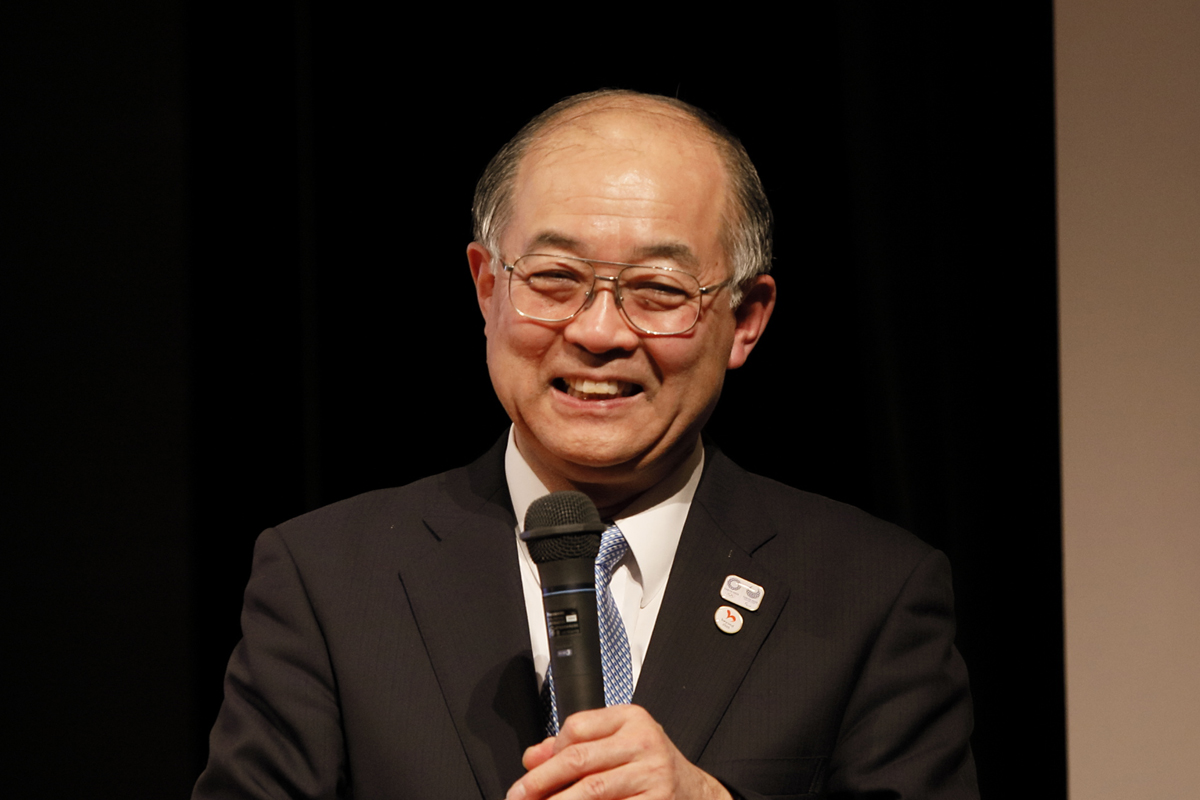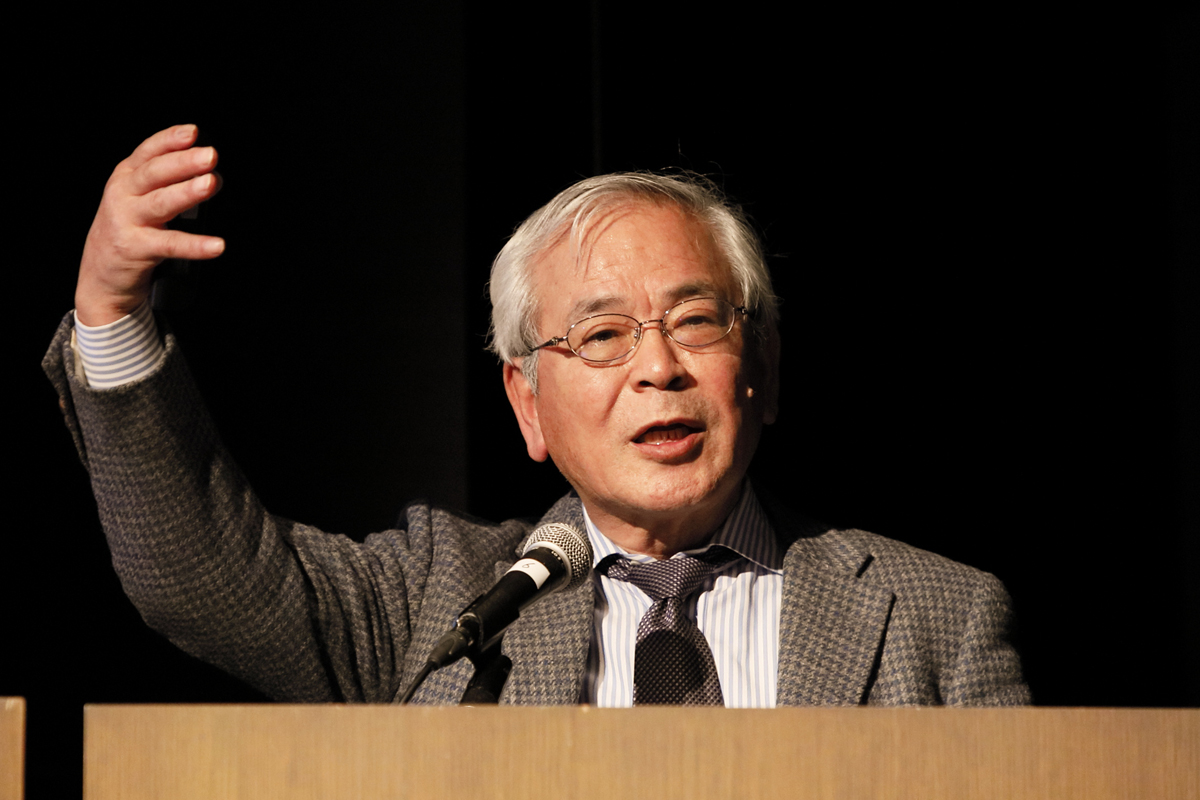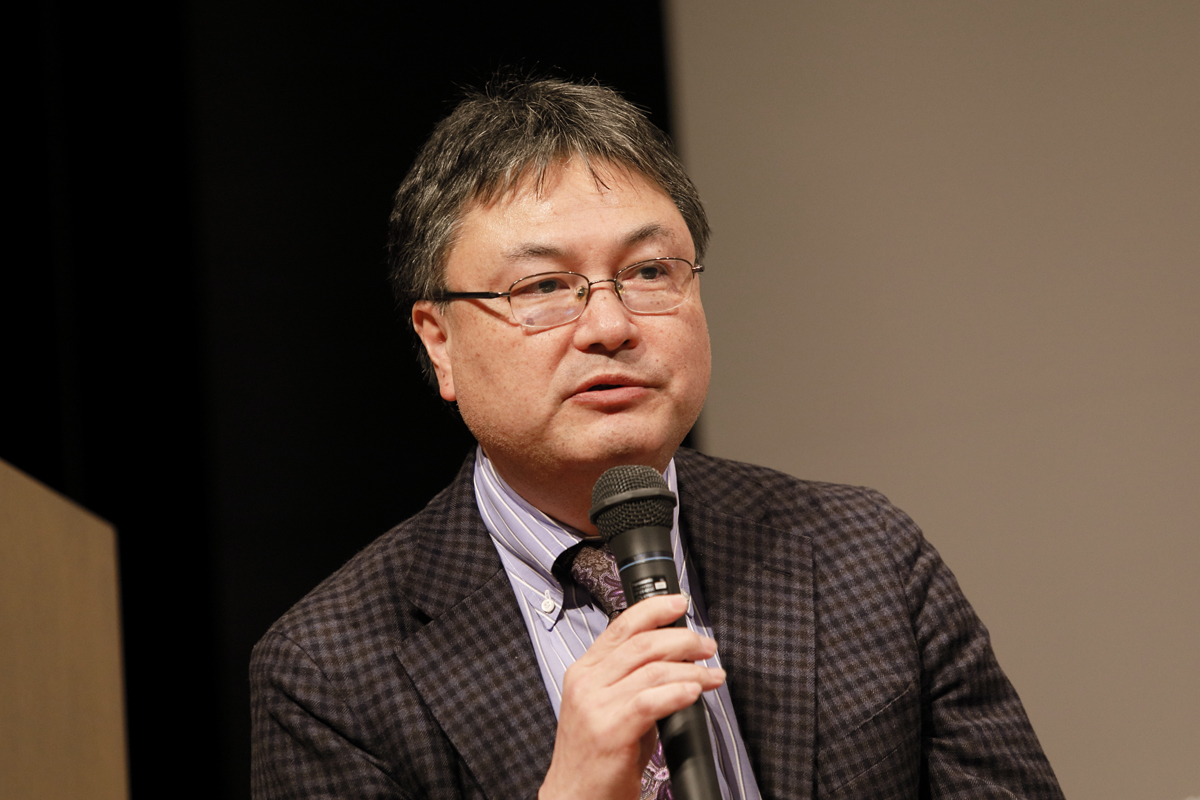-
主催者挨拶
 宮田 亮平文化庁長官
宮田 亮平文化庁長官 -
文化プログラム趣旨説明
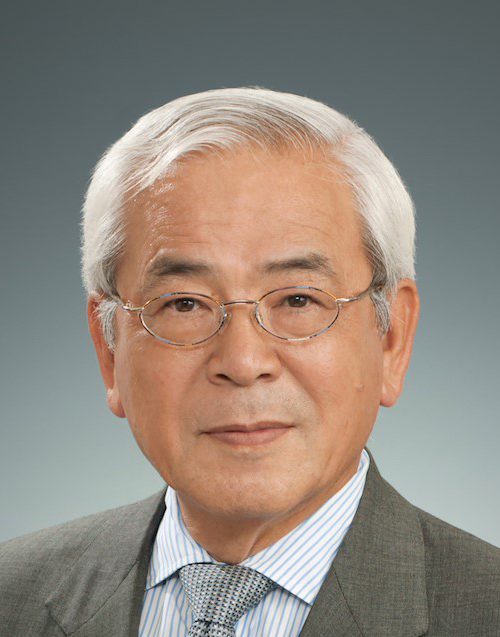 青柳 正規東京大学名誉教授/前文化庁長官/東京2020組織委員会文化・教育委員長
青柳 正規東京大学名誉教授/前文化庁長官/東京2020組織委員会文化・教育委員長 -
トークイベント
 岡本 信明横浜美術大学学長
岡本 信明横浜美術大学学長 -
トークイベント
 菅原 みこ横浜美術大学4年
菅原 みこ横浜美術大学4年 -
モデレーター
 太下 義之三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長/独立行政法人国立美術館理事
太下 義之三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長/独立行政法人国立美術館理事 -
プレゼンター
 神部 浩横浜市文化観光局文化プログラム推進部長
神部 浩横浜市文化観光局文化プログラム推進部長 -
プレゼンター
 アストリッド・クラインクライン ダイサム アーキテクツ 代表取締役
アストリッド・クラインクライン ダイサム アーキテクツ 代表取締役 -
プレゼンター
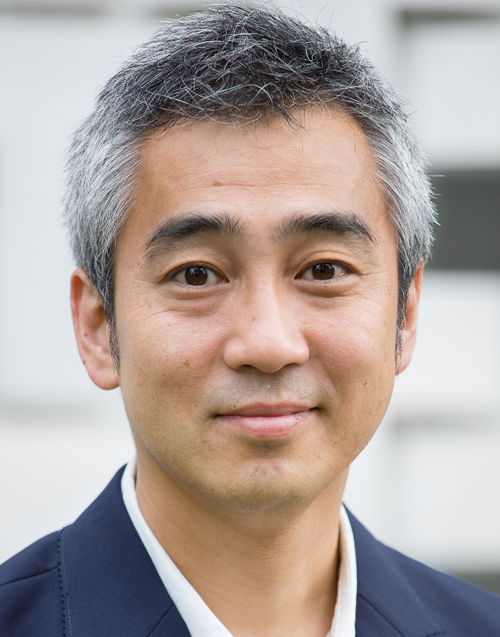 久山 幸成クライン ダイサム アーキテクツ シニアアーキテクト
久山 幸成クライン ダイサム アーキテクツ シニアアーキテクト -
プレゼンター
 川島 香(公社)日本芸能実演家団体協議会「ニッポンたからものプロジェクト」プロジェクトリーダー
川島 香(公社)日本芸能実演家団体協議会「ニッポンたからものプロジェクト」プロジェクトリーダー -
プレゼンター
 小池 真一(一社)共同通信社47文化プログラム・プロジェクトマネジャー
小池 真一(一社)共同通信社47文化プログラム・プロジェクトマネジャー -
プレゼンター
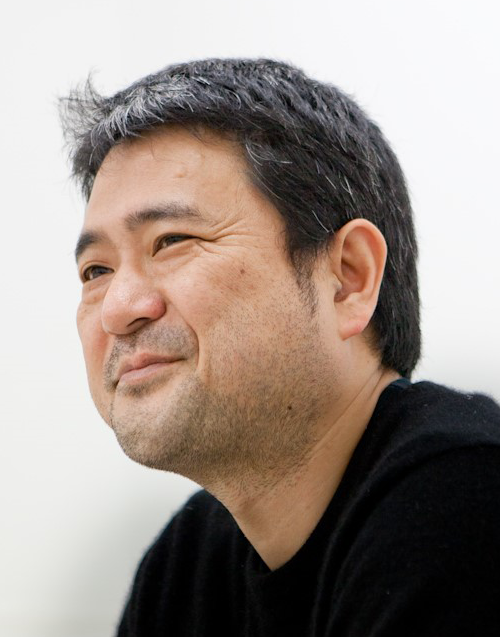 中村 政人(社)コマンドN代表理事/東京藝術大学美術学部教授
中村 政人(社)コマンドN代表理事/東京藝術大学美術学部教授 -
プレゼンター
 栗栖 良依SLOW LABEL ディレクター/ヨコハマ・パラトリエンナーレ総合ディレクター
栗栖 良依SLOW LABEL ディレクター/ヨコハマ・パラトリエンナーレ総合ディレクター

※本作は、日本財団DIVERSITY IN THE ARTS による事業の一環として制作され、2018年3月23~25日にシンガポールで開催されるアジア太平洋障害者芸術祭「TRUE COLOURS FESTIVAL」にて上演します。
いつかどこかで出会ったふたりの既視感。短くもはかない夜の物語。
-
宮田 亮平文化庁長官
-
岡本 信明横浜美術大学学長
-
菅原 みこ横浜美術大学4年
-
神部 浩横浜市文化観光局文化プログラム推進部長「ヨコハマトリエンナーレ2017島と星座とガラパゴス」
-
アストリッド・クライン/久山 幸成クライン ダイサム アーキテクツ 代表取締役 シニアアーキテクト「PechaKucha 20×20」
-
川島 香(公社)日本芸能実演家団体協議会「ニッポンたからものプロジェクト」プロジェクトリーダー「ニッポンたからものプロジェクト—日本遺産×Live Art—」
-
小池 真一(一社)共同通信社47文化プログラム・プロジェクトマネジャー「全国文化プログラムプレスセンター・プロジェクト」
-
中村 政人(社)コマンドN代表理事/東京藝術大学美術学部教授「プロジェクトスクール@3331」
-
栗栖 良依SLOW LABEL ディレクター/ヨコハマ・パラトリエンナーレ総合ディレクター「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」
-
モデレーター太下 義之三菱UFJリサーチ&コンサルティング 芸術・文化政策センター長/独立行政法人国立美術館理事
-
出演者青柳 正規、神部 浩、アストリッド・クライン、久山 幸成、川島 香、小池 真一、中村 政人、栗栖 良依
3回目となるCulture NIPPONシンポジウムは、横浜美術館にて開催された。
オープニングを飾ったのは、義足のダンサー森田かずよ氏と、定行夏海氏によるデュオのダンスパフォーマンス。身体と魂が混ざり共鳴し合うことで生まれる独特の世界観に会場一同引き込まれた。(本作品は日本財団DIVERSITY IN THE ARTS事業の一環として制作し、2018年3月23日~25日にシンガポールで開催されるアジア太平洋障害者芸術祭「TRUE COLOURS FESTIVAL」にて上演。)
引き続き、宮田亮平文化庁長官と、「beyond2020プログラム」ロゴマークをデザインした横浜美術大学4年の菅原みこさん、同大学学長の岡本信明氏が登壇し、ロゴマークトークイベントが行われた。菅原さんはデザインにあたり、「肯定」の意味を込めるとともに、言葉や国籍、年齢等の違いを超えて伝わるように、親指を立てた「いいね」のジェスチャーをモチーフにしたとコンセプトを説明した。それを受けて岡本学長は、世界をつなぐジェスチャーを用いた菅原さんのアイディアを評価するとともに、芸術系大学で蓄積された伝統を受け継ぎ、新生校である横浜美術大学から新たな動きが生まれたことへの感動を語った。
さて、今回のテーマは「文化プログラム事例発表会―2020年を越えて、担い手からのメッセージ―」。文化プログラムの優れた実践事例を担い手たち自らが紹介し、2020年の先への展望を語り合った。
紹介された文化プログラムとプレゼンターは次の6組である。それぞれの活動の概要とプレゼンターからのメッセージを記す。

3年に一度の国際現代アート展。2017年は88日間の会期で実施し26万人の来場者、障害のある方とその介護者は9000人の来場があった。「世界とつながる」「まちにひろがる」「アートでひらく」を目標に、特に障害のある方のためのバリアフリーアクセスガイドや、鑑賞ガイド、外国人向けの案内を充実させることができた意義は大きい。次回2020年は、世界から注目される機会をとらえ、さらなる海外への発信と、国籍や障害の有無等に関わらず誰もがアートを楽しめる取組を進めたい。

本業の設計事務所のかたわら、建築を超えたコミュニティデザインを考えて活動する中で、2003年に他のクリエイター仲間とPechaKucha Night(ペチャクチャナイト)というイベントを作った。20枚のスライド×20秒というフォーマットに従い、どんな人でもプレゼンテーションの機会が与えられる。ほどなく世界に広がり、現在1045の都市で運営されている。各地のネットワークが形成され、12000件のアーカイブがオンライン上で見られる。災害の時には地域がつながり、それぞれの声を聞くなど、ネットワークの強みが発揮された。東京で生まれ世界に広がったPechaKucha20×20を、2020年にぜひ盛り上げたい。

個性豊かな地域文化と日本の多彩な芸能(Live Art)を結びつけ、日本遺産を構成する寺院等を会場として伝統芸能を実演するという取り組みを2017年度に開始。「日本文化の再発見」「地域文化資源の活用と発信」「若手人材の育成」「次世代の教育」という4つのねらいがある。2017年度の公演で、地域住民や特に子どもたちが地域の「たからもの」である文化を知って、誇りや自信を持てるようになったという報告がある。2020年までに全国で開催していく。これをきっかけとして、全国で地域の魅力ある文化に多くの人が触れて、文化が教育や観光につながる動きが加速することを願う。

「中高生ジャーナリストが文化の力で地域を元気にする!」をコンセプトに、地元中高生らが地域文化や展覧会等を取材して、手作り新聞を作成し発信している。次世代を担う子ども達が主体的に表現・発信する機会を持つことで自分たちの文化プログラムであることを実感してほしい。「ニッポンたからものプロジェクト」の小浜公演と連携した取材会では、生徒たちが自分の街を好きになり、自信を取り戻し、地元に残って文化を発信したいと思うようになったという印象的な変化があった。47都道府県に広め、2020年には実際に中高生記者が一堂に会し、東京大会を取材する機会を作りたい。

アーツ千代田3331(旧中学校を改修したアーティスト主導の自律運営型のアートセンター)の実践ノウハウをもとに、アーツ・プロジェクトリーダーを育成するスクールを実施している。第一線で活躍する講師陣のもと、地域の宝である文化資源を持続的な価値創造にまで高めていくプロセスを実践まで学ぶ。経済性優先の考えでは地域社会は縮小していく。文化芸術のリテラシーを持って、地域に入っていき、縦社会に横串を刺して新しい仕事を作り出すリーダーを育成していく。

当初、横浜ランデヴープロジェクトとして、アーティストと障害者、職人、企業が出会うプラットフォームを開始したが、できる、できないで分かれてしまうものづくりに限界を感じるようになった。2014年にヨコハマ・パラトリエンナーレが誕生。アートにふることによって、もっと多くの人が関われるのではないかと考え、障害のある人の特性とプロのアーティストをかけ合わせるプロジェクトを開始した。パラトリエンナーレでは、例えば「障害のある人が参加したくてもできない」といった課題に対し、多くの人を巻き込んで仲間を増やしながら解決してきた。2020年以降は、パラトリではなく、障害のある人が当たり前にトリエンナーレに参加できる社会になってほしい。
続いて、6組のプレゼンターと、東京2020組織委員会文化・教育委員長青柳正規氏(東京大学名誉教授、前文化庁長官)が登壇し、太下義之氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長)をモデレーターにクロストークを行った。
2020年まで全国で展開される文化プログラムは、“beyond”という言葉の意味にも表されているように、2020年のその先に目標がある。あらためて2020年以降のために残していくべきレガシーは何か。またそのために2020年までの期間に何をするべきなのか。
一点目に挙げられたのは、誇りの醸成である。都市部の芸術祭も、都市部以外の地域に根差した文化も、そこに暮らす人達や未来を担う子ども達にとって、街を好きになり誇りをもつ核になり得る点で共通している。また、身近な所でクリエイティブな人が直接集まり話せる場を作ることだけでも、まちが面白くなっていく。文化プログラムは、住み続けたいと感じる魅力あるまちを作り、住民の誇りや自信を生み出すきっかけになり、それが2020年以降の豊かな地域社会につながる可能性を持つ。
二点目に、人を巻き込むことである。文化プログラムを実施するうえで生じる文化分野以外のセクターとの協働や、地域の様々な関係者との協働は、苦労も多いがこれまでに接続していなかった分野との関係作りに直結する。2020年までの文化プログラムの実施を通じて築かれる他分野との関係が、2020年以降の分野を超えた連携の素地にもなる。
また、アートのプログラムをまちの人達と関係を作って動かしていく必要性も語られた。様々な課題に目を背けずそこに住む人々と議論し、今後の社会のために何をしていくべきかを共に考えることが重要で、そこで紡がれる信頼関係が、地域住民とアートの関係をより豊かなものにしていく。
三点目に、文化に対する意識改革である。ロンドン大会の文化プログラムのディレクターメンバーが来日した際、一番のレガシーは国民の文化に対する意識が変わったこと、と語ったそうである。文化プログラムにより文化活動への理解が促進され、文化が持つ幅広い意義・重要性に対し意識改革が起こるならば、2020年以降の社会における文化の位置づけが確実に変わるだろう。
四点目に、共生社会に向けた動きである。栗栖氏は、2020年までに、共生社会実現に必要な人材育成や技術の開発と、そのネットワーク作りを行うとともに、海外と連携したり地域へ人材を送りだしたりするための拠点を作る構想を語った。ヨコハマトリエンナーレの神部氏は2020東京大会に向けた文化プログラムという機会が、シームレスな社会に転換するためのエンジンになっていると指摘する。2020年東京大会という契機が今後の共生社会へ大きなインパクトをもたらすことは間違いない。
また、各事例をかけ合わせることで相乗効果が期待できるのではないか、という提案が飛び出した。クライン氏がPechaKuchaはグローバルなプラットフォームであり、今回のプレゼンなども世界でシェアできると指摘すると、川島氏は、「ニッポンたからものプロジェクト」の伝統芸能公演や、子どもたちがお寺で企画するPechaKuchaなど、日本ならではのコンテンツを発信することの意義は大きいと呼応した。コンテンツとプラットフォームが組み合わせられることで、地域文化や芸能など外国人に知られていない日本の文化の魅力を海外に発信できる可能性が広がるであろう。
最後に青柳氏は、2020年を契機に自分たちの住んでいる地域の生活様式や風土、お祭り等の文化を総点検し、グローバルな社会の中で他国と相対化して文化を理解することができる日本になることが一番のレガシーであり、それによりもっと日本は豊かでしなやかで優しい、将来に自信を持てる国になるのではないかと呼びかけ、シンポジウムを締めくくった。
文化庁地域文化創生本部 総括・政策研究グループ
研究官