


-
パネリスト宮田 亮平文化庁長官
 1945年、新潟県生まれ。金工作家。東京藝術大学の学長を10年務めた後、2016年4月より文化庁長官に就任。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズなどで知られ、2012年には日本芸術院賞を受賞している。
1945年、新潟県生まれ。金工作家。東京藝術大学の学長を10年務めた後、2016年4月より文化庁長官に就任。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズなどで知られ、2012年には日本芸術院賞を受賞している。 -
パネリスト吉本 光宏東京2020組織委員会文化・教育委員、ニッセイ基礎研究所研究理事
 1958年、徳島県生まれ。文化施設開発やアート計画のコンサルタントとして活躍する他、文化政策や創造都市、五輪文化プログラム等の調査研究に携わる。現在、文化審議会文化政策部会委員、企業メセナ協議会理事、東京藝術大学非常勤講師等。
1958年、徳島県生まれ。文化施設開発やアート計画のコンサルタントとして活躍する他、文化政策や創造都市、五輪文化プログラム等の調査研究に携わる。現在、文化審議会文化政策部会委員、企業メセナ協議会理事、東京藝術大学非常勤講師等。 -
パネリスト日比野 克彦東京藝術大学美術学部長
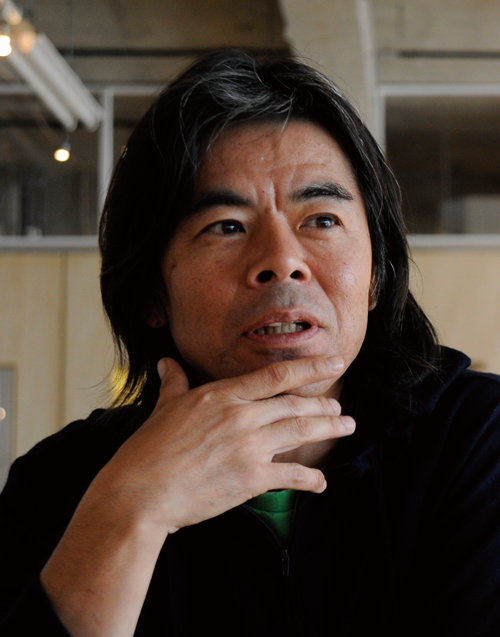 1958年、岐阜県生まれ。東京藝術大学大学院修了。82年日本グラフィック展大賞受賞。平成27年度芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)。地域性を活かしたアート活動を展開。現在、先端芸術表現科教授。岐阜県美術館長。
1958年、岐阜県生まれ。東京藝術大学大学院修了。82年日本グラフィック展大賞受賞。平成27年度芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)。地域性を活かしたアート活動を展開。現在、先端芸術表現科教授。岐阜県美術館長。 -
パネリスト清川 進也音楽家、プロデューサー
 1976年、福岡県生まれ。「拡張音楽」をコンセプトに音楽の新たな機能性を追求する音楽家。2011年に故郷で制作した「森の木琴」がカンヌ国際広告祭3冠。音楽以外でも精力的に活動を行い、「別府市・湯~園地計画!」では全行程の総合監修を務めた。
1976年、福岡県生まれ。「拡張音楽」をコンセプトに音楽の新たな機能性を追求する音楽家。2011年に故郷で制作した「森の木琴」がカンヌ国際広告祭3冠。音楽以外でも精力的に活動を行い、「別府市・湯~園地計画!」では全行程の総合監修を務めた。 -
モデレーター山出 淳也NPO法人BEPPU PROJECT代表理事、アーティスト
 1970年、大分県生まれ。2005年にBEPPU PROJECTを設立。別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」「in BEPPU」等の地域性を活かした芸術祭を開催。平成20年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞(芸術振興部門)。
1970年、大分県生まれ。2005年にBEPPU PROJECTを設立。別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」「in BEPPU」等の地域性を活かした芸術祭を開催。平成20年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞(芸術振興部門)。 -

Culture NIPPONとは、文化庁が2020年に向けて全国各地の文化プログラム等の情報を集約・発信するポータルサイトです。あなたの文化プログラムもぜひ登録ください!

2018年秋に国民文化祭開幕をひかえる大分県で開催されたCulture NIPPONシンポジウムのテーマは、「共に創る文化プログラム 2020年以降へのレガシーを目指して」。冒頭に宮田亮平文化庁長官は、現在5141校の学校、約6万人(いずれも本シンポジウム開催時点)の小学生が参加する動きとなっている東京2020大会マスコット選定の投票について紹介し、多くの人々が参画できる仕組みを通じて、全国で東京大会に向け機運を醸成しようと呼びかけた。
当シンポジウムでは、吉本光宏氏(東京2020組織委員会文化・教育委員、ニッセイ基礎研究所研究理事)、日比野克彦氏(東京藝術大学美術学部長)、清川進也氏(音楽家、プロデューサー)、山出淳也氏(NPO法人BEPPU PROJECT代表理事、アーティスト)の4名のパネリストによるショートプレゼンテーションに続き、宮田長官を交え山出氏がモデレーターを務めたパネルディスカッションが行われ、多くの人が関わり共に創りあげていく文化プログラムとなるための具体的なアイディアや、2020年以降のレガシーにつなげていくための方策について白熱した議論が交わされた。

吉本氏は、ロンドン大会の文化プログラムの事例を紹介し、その特徴としてロンドンだけでなく英国全土1000カ所以上で行われたこと、文化を通じて誰もが参加できることを目指すプログラムが展開されたこと、とりわけ若者に対し創造性を喚起し誇りを与えるきっかけになったこと等を取り上げた。そのうえで、日本の文化プログラムでは「オリンピック・パラリンピックでしか出来ないこと」-例えば、市民参加、子どもたちやお年寄りの記憶に残ること、平和の追求-といったテーマを重視すべきであると提案した。また、文化プログラムは東京のためではなく各地域のために展開されるべきであり、そのために最も重要なことは、地域にとっての文化芸術の役割を考え直すことであると主張。それはとりもなおさず長期的な地域の文化ビジョンを構想することである。
地域において具体的にどのようなプログラムを展開することが望まれるのか。宮田長官は、例えば大分県の竹文化のように、地域に根差しつつ世界に誇れるものを発信することが重要であるとし、「一番大事なことは地方のよさを出すこと」と強調した。

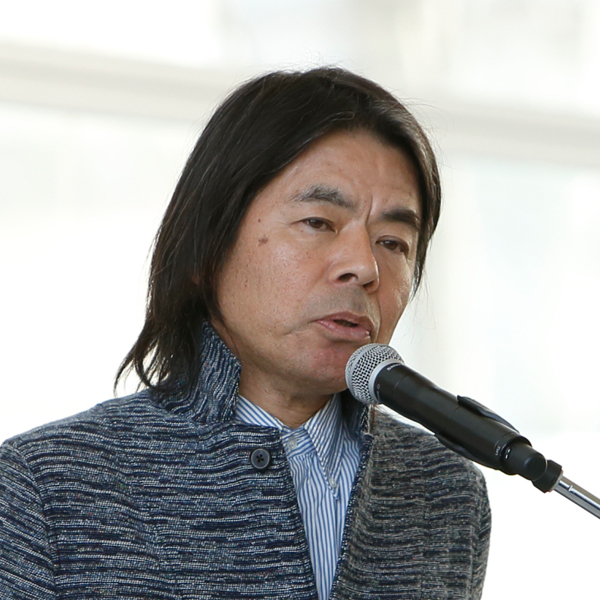
日比野氏は、自身が監修を務める『TURN』の取り組みについてプレゼンテーションを行った。東京都の文化プログラムのひとつである『TURN』は、障害者施設・コミュニティ等にアーティストが訪れて関わり、多様な人々の出会いを生み出すプログラムである。アーティストが福祉施設等に入ることによって起こる変化について日比野氏は、施設側、アーティスト側の双方に意味があるという。福祉施設はともすると閉じた空間になりがちであるが、アーティストが入ることで井戸端会議的に会話が生まれ、新しい空気を送り込むことになる。福祉もアートも、相手がどう受け止めるかを想像するコミュニケーションやシミュレーションが重要である点が共通しており、アーティスト側にとっても気づきがある。その意味で福祉施設は文化施設である、と日比野氏は語る。ここで活かされる美術の特性の一つは、「答えがひとつではない」ということであり、アートは社会の中に違う視点を投げかけることができる。日比野氏は、人と人との関係性や社会のあり方を変えていくこと、世の中の価値観を多様化することこそが2020年東京大会以降の社会に残すべきレガシーであると主張した。
パラリンピックの意味合いがこれまで以上に重要性を増しているのと同様、障害者や高齢者など社会的弱者と呼ばれる人々の力をどう社会にいかしていくのかをアートを通じ探求する文化プログラムは大きな重要性を持つだろう。山出氏は、2020年を契機に社会に問いかける力にしていくために、すでに行われている個々の活動同士の横の連携を作る必要性についても言及した。

自身が総合監修を手掛けた「別府市・湯~園地計画!」についてプレゼンテーションを行った清川氏は、この企画のポイントは「Mash up(異なる2つのものをかけあわせて新しいものを作りだすこと)」にあるという。つまり「温泉」と「遊園地」という異なる2つの機能をかけ合わせることで、より面白く多くの人をひきつけるものに生まれ変わらせた。既存の施設が持つ本来の目的をずらして目的外使用することに、新しい可能性やイノベーションにつながるヒントがある。
また、3日間の限定オープンで、ボランティアスタッフ数は1200人にものぼった。これだけの市民が参加した理由について清川氏は、自らが面白い、楽しいと感じることを自分たちで実現したいという「自分事」の意識を生み出せたことに起因するのではないかと分析する。このような参加の仕組みは、これから文化プログラムを全国展開していくうえでも参考になるものであろう。
オリンピック・パラリンピック大会の競技はある瞬間に終わり、スタジアムには限られた人しか入ることができない。それに対し、文化プログラムにはすべての国民が参加でき、かつ来るべき地域の未来を自分たちで作っていく枠組みになり得るという重要な役割がある。文化プログラムを共に創る機運を醸成するためにどうすれば良いのか。
1964年の東京オリンピックがピンと来ない世代である清川氏は、同世代の多くがまだオリンピックを自分事と捉えられていないと危惧する。現代ならではの新しいメディアを使って、例えば誰もが一選手になれるような参加の仕組みがあると良いのではと投げかけた。また日比野氏は、多様な人やものが交流することで生まれるのが文化であり、これから2020年の本番を迎えるまでの間にどれだけの人々が「ワクワクする時間」を持てるのかが大事であるという。それを受けて吉本氏は、文化プログラムの主催者になって自分でワクワクすることもオリンピックへの参加の一方策であるとし、「自分事」として自分たちでやろうとする人が2020年までにどれだけ生まれるかが、その後の地域が面白くなるかどうかを決定づけていくことになると指摘した。
シンポジウム全般を通して浮かび上がったキーワードは「参加」、「交流」、「多様性」、「自分事」である。各地域で各市町村や全国民が、文化でどのような未来を作っていきたいのか、自分がどうワクワクしたいのかを考え、自分事にしていくこと。そしてそれが全国的な展開となり繋がりが生まれることが、文化プログラムを契機に地方が輝いていくための重要な要素になることを確認し、シンポジウムは閉会した。
文化庁地域文化創生本部 総括・政策研究グループ
研究官






